近年、先進諸国を中心に高齢化が進むなか、薬物使用障害(Drug Use Disorders:DUDs)が高齢者の間で増え続けていることがわかってきました。慢性疼痛や精神的ストレスを背景に処方薬や違法薬物の使用が広がり、健康への影響は無視できないレベルに達しています。2025年に BMC Geriatricsに掲載された新しい研究では、”世界疾病負担研究(GBD)2021”のデータを用いて、60〜89歳の高齢者における薬物使用障害(依存症)の世界的な動向が詳しく分析されました。対象はオピオイド(医療用麻薬)、コカイン、アンフェタミン(覚せい剤)、大麻の4種類です。
・30年間のデータで見えたこと
研究チームは1990年から2021年までのデータを解析し、次のことがわかりました。
①最も負担が大きいのはオピオイド使用障害
2021年時点で、障害調整生命年(DALYs)は10万人あたり67.8(注)。北米では特に急増傾向です。
②コカインやアンフェタミンも微増
高所得地域(米国や西ヨーロッパ)で負担が拡大していました。
③カンナビス使用障害は比較的安定
他の薬物と比べ負担が低く、増加率も限定的でした。
・なぜ高齢者で薬物依存が増えているのか?
特に北米では疫学的変化(薬物の入手や使用パターンの変化)が大きく影響していました。
背景には次のような事情があります:
慢性疼痛管理でのオピオイド処方増加(特に1990年代後半以降の米国)
違法薬物(ヘロインやフェンタニル)の流通
高齢者の孤独・社会的孤立が薬物依存リスクを高めている
一方で、中国など中高所得国では薬物規制や疼痛管理プログラムの強化が功を奏し、負担が減少傾向にあります。
・高齢者と大麻 比較的安全な選択肢?
注目すべきは、大麻使用障害の負担が他の薬物に比べて低く安定している点です。過去10年での大麻の規制緩和とアクセスの向上を考慮すると、使用者自体は劇的に増加しているにもかかわらず、です。近年の報告では、高齢者における大麻使用は重篤な副作用が少なく、疼痛や不眠、不安の緩和に有効な場合があるとされています。依存リスクもオピオイドやアンフェタミンと比べ低く、適切な管理下での使用は比較的安全性が高いという論調が広がっています。こうした知見は慢性疼痛や不眠に悩む高齢者がオピオイド依存に陥るリスクを下げる代替手段としての大麻利用の可能性を示唆しています。
・2035年までの予測
予測モデルによると、世界全体で薬物使用障害による負担は今後も増加し、特に北米の高齢男性で顕著な上昇が見込まれています。
・何が必要か?
高齢者向けの薬物乱用予防・治療プログラムの整備
疼痛管理方針の見直しと適正処方の徹底
安全な代替療法(例:医療用大麻)の検討
社会的孤立への対策(地域での支援体制づくり)
薬物使用障害は若者だけの問題ではありません。高齢者の健康と生活の質を守るための取り組みが求められています。
参考:Jia B, Wei R, Li Z, et al. *Global and regional burden of four drug use disorders in the elderly, 1990 to 2021: an analysis of the Global Burden of Disease Study.* BMC Geriatrics. 2025;25:434.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12220652/pdf/12877_2025_Article_6075.pdf
(※注:障害調整生命年(DALYs:Disability-Adjusted Life Years)は、「ある健康問題が人々の生命と生活の質に与える総合的な負担」を年数で表した指標です。より具体的には、次の2つの要素を合計して算出されます:①早死による損失年数(YLL:Years of Life Lost)その疾病や障害によって本来より早く死亡した分の年数 例:本来80歳まで生きられるところを60歳で亡くなった場合、YLLは20年
②:障害を伴って過ごす年数(YLD:Years Lived with Disability)病気や障害のために健康な状態で過ごせなかった期間を、重症度で重み付けして年数化 例:生活の質が50%に低下した状態で10年間生きた場合、YLDは5年
DALYs = YLL + YLD、つまり、その病気や障害が「寿命を縮めた分」+「健康な生活を損なった分」を合計したものになる。)
執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年8月3日
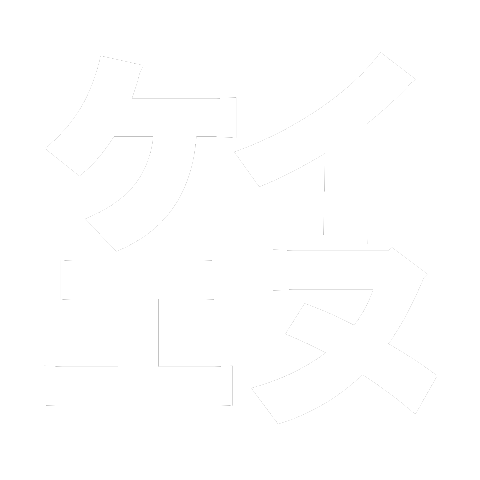

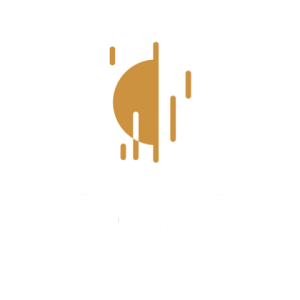
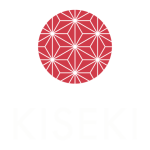
コメントを残す