大麻由来の成分といえば、多くの人がまず思い浮かべるのは精神活性作用を持つ THCです。THCは「ハイ」を引き起こす一方で、短期的に記憶力や注意力を低下させることが知られています。
一方、CBDには精神活性作用がなく、抗炎症作用や抗酸化作用、神経保護作用を持つと報告されています。そのため、不安障害や睡眠障害、神経変性疾患などへの応用が期待されてきました。
CBDが人間の認知機能にどのような影響を及ぼすのかについて、これまでのヒトを対象とした無作為化比較試験(RCT)を体系的にまとめた研究を紹介します。
・研究の概要
著者らはPubMed/Medlineを用いて徹底的な文献検索を行い、1038本の論文の中から最終的に 36本のRCT を選出しました。対象となったのは以下のような幅広い人々です。
健康な被験者
パーキンソン病患者
精神疾患患者(不安障害、PTSDなど)
統合失調症患者
物質使用障害患者
試験では、経口カプセル、オイル、吸入(電子タバコ)などさまざまな投与経路が用いられ、投与量は75mgから1000mg以上と幅がありました。
・健康な参加者での効果
健常者を対象とした研究は特に多く、単回投与での脳機能測定が中心でした。
600mgのCBD単回投与を受けた被験者を対象にしたfMRI研究では、脳内のネットワーク活動に一部変化が見られたものの、認知機能テストの成績には明確な改善(および悪化)は確認されませんでした。一方、模擬スピーチ課題(社会不安を誘発する試験)では、CBDを投与された群で不安感や認知的負荷が軽減したと報告されました。低用量(例:12.5mgを含む電子タバコ吸入)では、言語記憶の成績が改善したとする研究も認められました。
このように、健常者では「強い効果はないが、状況によっては認知や不安関連症状にプラスの作用がある」ことが示唆されました。
・パーキンソン病患者
パーキンソン病では、CBD投与(75〜300mg/日)が日常生活動作に軽度の改善をもたらしたとされています。特に睡眠の質や不安の軽減に寄与する可能性がありますが、認知機能そのものに対する効果は限定的でした。
・精神疾患におけるCBD
精神疾患領域では、不安障害やPTSDを対象にした研究が多く存在します。
300〜400mgのCBD投与で、患者の主観的不安が有意に低下しました。PTSD患者に対しては、100mg程度の比較的低用量でも睡眠の質の改善や気分の安定が見られました。これらは直接的な「認知改善」ではなく、むしろ周辺症状の改善を通じて認知機能に良い影響を与える可能性が示唆されています。
・統合失調症
統合失調症や精神病症状を持つ患者に対しては、600〜1000mgと比較的高用量のCBDが投与されました。一部の研究では妄想や幻覚といった症状の改善が報告されましたが、認知機能(記憶や注意力)の改善効果はほとんど確認されなかったとのことです。また、CBDはTHCによる精神症状を打ち消す作用を持つ可能性も指摘されています。
・物質使用障害
アルコールや大麻などの使用障害患者に対する研究ではCBDは強い効果を示さず、認知機能改善はほとんど確認されなかったとされています。ただし、安全性の面では問題がなく、副作用も軽度でした。
・全体のまとめと課題
本レビューの結論として、CBDの認知・精神機能に対する影響は以下のように整理できます。
健常者:大きな認知機能改善効果は見られないが、特定状況(不安誘発課題など)では有効性あり。
神経疾患(パーキンソン病):生活の質向上や睡眠改善はあるが、認知機能改善は限定的。
精神疾患(不安障害・PTSD):不安や睡眠に効果が見られ、間接的に認知へ好影響の可能性。
統合失調症:陽性症状の軽減は一部報告されるが、認知改善効果は弱い。
物質使用障害:認知機能への効果は限定的。
重要な限界として、投与量や方法の統一性がなく、研究ごとにバラバラであること、多くが単回投与試験であり、長期的な効果が検証されていないこと、認知機能の評価方法も多様で、結果の比較が難しいことが挙げられています。
・今後の展望
CBDは安全性が高く、副作用が軽度である点は臨床応用において大きな利点です。ただし、認知機能改善の薬としての科学的根拠はまだ不十分であり、標準化された投与デザインを用いた長期的研究が必要とされています。
特に、不安障害やPTSDなどでの周辺症状改善を介した認知機能への影響、高齢者や神経変性疾患患者での長期的な効果、THCとの相互作用による認知保護作用、といったテーマは、今後の注目すべき研究領域となるでしょう。
また重要な点は、認知症患者を対象にした研究というのは現時点では行われていないということです。これは今後の取り組みに期待が集まります。
・おわりに
CBDは「副作用の少ない安心できる大麻成分」として注目を集めていますが、その認知機能への影響は不明確です。ただし、不安や睡眠といった要素にプラスに働くことは複数の研究で示されており、今後の臨床応用に向けて大きな可能性を秘めています。CBD市場が急速に拡大する中、科学的エビデンスに基づいた正しい理解が求められます。
執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年9月1日
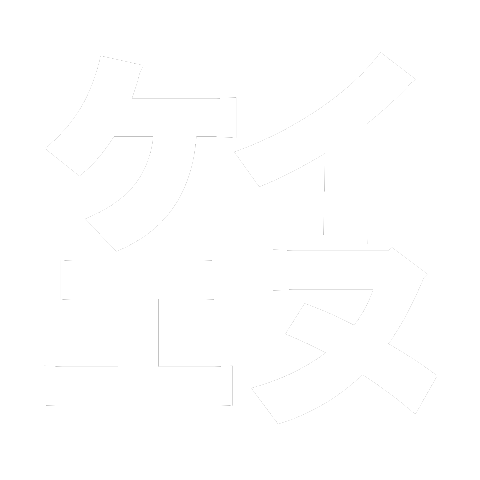

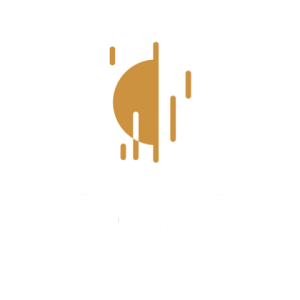
コメントを残す