妊娠や授乳期にカンナビス(大麻)を使うことは、医療・家族・社会のいずれからも強い視線を浴びやすいテーマです。リスクの話は耳にする一方で、つわりや痛み、不安の軽減などを目的に実際に使い続ける人がいるのも事実です。今回ご紹介する論文は、妊娠・育児系サイトの専用フォーラムに寄せられた会話を読み解き、「スティグマ(烙印)」が当事者の暮らしや行動にどう影響しているのかを丁寧に掘り下げています。ここでは、専門用語はできるだけ噛み砕きつつ、論文のポイントをカジュアルめにまとめます。
・この研究、何をしたの?(ざっくり概要)
対象:妊娠・授乳×カンナビスのトピックを扱うオンライン掲示板
期間:2020年6月〜2021年5月
方法:各月10スレッドを無作為抽出(合計120)。内容を確認し、最終的に113スレッドを質的に分析
狙い:「スティグマがどう語られ、どう受け止められているか」「その結果、当事者の行動(相談や受診など)がどう変わるのか」を、当事者の“生の声”から明らかにすること
分析は、まずトピック別に粗く分類し(サイクル1)、その後に意味や背景の共通点でまとめ直す(サイクル2)という二段構えで行われました。複数の研究者が読み合わせをして合意形成しているので、恣意的な解釈に寄りすぎないよう配慮されています。
・見えてきたのは大きく3つのテーマ
1) スティグマの経験(いちばん手前にある痛み)
まず目につくのは、家族・パートナー・義家族・友人・職場など、日常の近い関係からの否定的な反応です。「成長しろ」「親になる自覚が足りない」といった説教調の言葉、無言の圧、冷たい視線。そこから生まれる羞恥、罪悪感、怒り、やるせなさ。こうした感情の揺れが何度も語られていました。一方、掲示板の中では「ここではジャッジされない」「安心して話せる」と感じる人が多く、”逃げ場”や“居場所”としての機能がはっきり見えます。つらい気持ちを吐き出せて、少し楽になったという声も。
2) ダブルスタンダードへの違和感(アルコールやタバコと比べて)
次に多かったのが、アルコールやタバコとの比較です。「妊娠中に飲酒する人はそこまで責められないのに、どうしてカンナビスだけは“絶対ダメ”の空気になるの?」という疑問や不満が繰り返し書かれていました。家族内でタバコを吸う人が、カンナビスを強く責める――そんな偽善っぽさ”への指摘もちらほら。社会のルールやメッセージが一貫していないことが、当事者の混乱と孤立感を深めているようです。
3) スティグマへの挑戦(語り合い・励まし・根拠探し)
掲示板では、経験の共有と相互のエンパワメントが起きています。「妊娠中に大麻を使っていたけど、うちの子は元気に育っている」「こういう資料があるよ」など、肯定的な体験談や外部情報の紹介が、スティグマに対抗する実践として機能していました。もちろん、経験談は科学的エビデンスと整合しないこともあるので、その扱いは慎重さが必要ですが、孤立をやわらげる力があるのは間違いありません。
・そもそも、なぜスティグマが問題なの?
ポイントは、スティグマそのものが健康リスクを増幅しうることです。
「責められるのが怖い」「恥ずかしい」と感じると、医療者に正直に話せなくなる→早めの介入やサポートにつながらない→結果的に母子のリスクが高まる、という悪循環が起きがちです。さらに、社会のメッセージがバラバラだと、家族内の対立や不信も生じやすく、支援ネットワークが崩れる可能性があります。リスクを減らすためには、非難ではなく、現実的な対話と情報提供が大切です。
・医療現場・支援者・家族にとってのヒント
1. まず“聴く”スタンスを
道徳的な評価や説教よりも事実ベースのリスク説明+当事者の語りへの共感が先です。「やめろ」から入るより、「どうして必要だと感じたのか」「今どんな不安があるのか」を聞く方が、結果的に安全につながりやすくなります。
2. メッセージを“そろえる”
カンナビス、アルコール、タバコなど、全部まとめて一貫した啓発を実施することが重要です。曖昧な情報が残ると、当事者は“都合のよい情報”だけをつまみ食いしがちです。分かりやすい最新の根拠にもとづく資料を案内しましょう。
3. コミュニティを“味方”に
オンラインコミュニティーには孤立を減らす力があります。信頼できる情報を橋渡しできると、誤情報の拡散を抑えつつ、当事者の自己効力感を高められます。医療機関や支援団体のリンク集、FAQ、相談窓口の紹介など、小さな仕掛けでも効果的です。
・研究の限界点
匿名掲示板ゆえのバイアス:参加者像が限定的で、肯定的な声が集まりやすい
時期の特殊性:2020〜2021年(コロナ禍)という状況が会話に影響している可能性
サンプルの範囲:1サイト・1年・113スレッドというスケールの制約
つまり、「ネットに書かれたこと=現実の全体像」ではありません。ただし、“声が表に出にくい人たち”の視点を可視化したという点で、価値は大きいといえます。
・まとめ:非難より支援へ、沈黙より対話へ
この研究から伝わってくるのは、スティグマが人を黙らせ、ケアから遠ざけるという現実です。リスクの話はもちろん必要ですが、伝え方が非審判的であるほど、当事者は正直に話し、助けを求めやすくなります。
妊婦さん本人、パートナー、家族、医療者、支援者――それぞれの立場でできることは違います。でもゴールは同じ。母子の安全と健康を守ることです。非難より支援、沈黙より対話。その一歩目は、「まずは話を聞かせてください」というシンプルな言葉から始まるのだと思います。
※本記事は学術情報の紹介であり、個別の医療判断を置き換えるものではありません。気になる方は、信頼できる医療者や支援窓口にご相談ください。
執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年8月12日
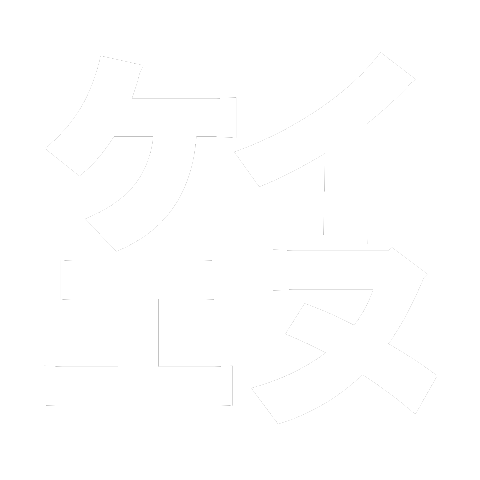

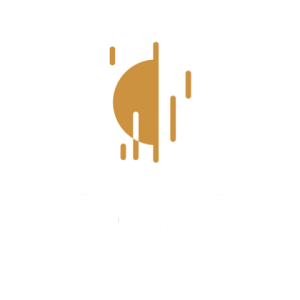
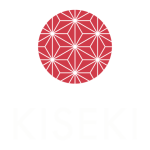
コメントを残す