・はじめに
アルコール使用障害(Alcohol Use Disorder, AUD)は、若者に深刻な影響を及ぼす精神疾患の一つです。米国では18歳までに約15%が診断基準を満たすとされ、日本でも大学生や若年層の飲酒に関するリスクが社会問題化しています。従来の治療は認知行動療法や家族療法、動機づけ面接などの心理社会的アプローチが中心ですが、その効果は必ずしも十分ではなく、新しい治療法の開発が求められています。
そこで注目を集めているのが、大麻草由来のCBDです。CBDは陶酔作用を持たず、安全性が高く、抗不安作用や抗炎症作用など多様な可能性が示されています。動物実験ではアルコール摂取の抑制や再発予防、神経毒性の軽減効果が報告されてきました。しかし人間、特に若者を対象とした臨床データは限られており、その有効性は未知数です。
今回紹介する米国サウスカロライナ医科大学の研究は、CBDの急性効果を検証するために設計された世界初の十分な規模を持つ臨床試験です。本記事ではその内容を解説し、なぜ「単回投与」というデザインが採用されたのか、そしてそこから見えてきた意義と課題を考察します。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40500407/
・試験デザインの概要
研究は17〜22歳のAUDを持つ36名を対象に、クロスオーバー型二重盲検プラセボ対照試験として行われました。参加者は CBD 600mg(Epidiolex製剤)または プラセボ(ゴマ油+イチゴ香料)を摂取し、18日以上のウォッシュアウト期間を挟んで両方を体験しました。投与前には脂肪分70%のスナックを摂取してCBDの吸収率を高め、投与から2〜3時間後(血中濃度のピークに相当)に各種検査を実施しました。評価項目は以下の4点です。
1:脳内神経化学物質の測定(Glx・GABA濃度、1H-MRS)
2: アルコール関連の脳反応(fMRIによるアルコール画像への反応)
3:心理生理学的反応(アルコールの匂いに対する心拍変動・皮膚電気反応・自己申告欲求)
4: 投与後7日間の飲酒行動(日記形式の報告)
安全性は医師による診察と有害事象モニタリングで確認されました。
・なぜ単回投与なのか?
多くの読者が「なぜ慢性投与ではなく一度きりの投与なのか?」と疑問に感じるかもしれません。この研究が単回投与を選んだ理由には、いくつかの背景があります。
1:安全性の確認
若者のAUD患者にCBDを投与した前例はなく、まずは短期間で安全性を確認する必要がありました。急性投与ならリスクを最小限に抑えつつ、安全性のデータを収集できます。
2:薬理シグナルの探索
過去の成人や他疾患の研究では、600mgの単回投与で神経化学物質の変化(グルタミン酸やGABAのレベル変化)が確認されています。研究者は同様の「急性効果」が若者AUDでも見られるかを検証しようとしました。
3:スクリーニング試験という位置づけ
著者らは本試験を「medication screening」と位置づけています。これは治療効果を確定するのではなく、薬剤が作用する兆候(シグナル)を効率的に確認する段階です。そのため、まず単回投与で神経や心理の変化を捉えようとしたのです。
4:倫理的・実務的配慮
未成年を含む若者に長期間薬剤を投与するのはリスクが高く、倫理的にもハードルがあります。まず短期投与で安全性と耐容性を確認し、次に慢性投与試験へ進めるのが妥当だと考えられました。
・結果のまとめ
神経化学物質:CBD投与によるGlxやGABA濃度の有意な変化は認められず。ただしAUD症状数やビンジ飲酒日数と神経代謝の関連は確認されました。
脳の反応:アルコール画像への神経反応にCBDの効果はなし。
心理生理学的反応:アルコールの匂いに対する飲酒欲求は高まったが、CBDの抑制効果はなし。心拍変動や皮膚反応も差なし。
飲酒行動:投与後7日間の飲酒状況に有意差なし。
安全性:有害事象は一切報告されず、安全性は良好。
・考察:単回投与デザインの限界
今回の結果は「CBDは若者AUDに急性効果を示さない」というものでした。これは一見すると否定的な結論ですが、背景を踏まえると重要な示唆を含んでいます。
・急性投与では変化を捉えにくい
AUDは慢性的な神経適応を伴う疾患であり、単回投与で顕著な効果を得るのは難しいと考えられます。CBDが作用するには反復投与や長期的介入が必要かもしれません。
・刺激の不十分さ
fMRIで用いたアルコール画像や匂い刺激は、若者にとって十分に飲酒欲求を引き起こすものではなかった可能性があります。強い環境刺激や味覚刺激の方が効果を検出しやすいかもしれません。
・バイオアベイラビリティの個人差
CBDは吸収率に大きな個人差があり、本研究では血中濃度を測定していません。効果の有無を正確に判断するには血中濃度との関連を評価する必要があります。
・本研究の意義
本試験の最大の成果は、若者のAUDにおいてCBDが単回投与で即効性を持たないことを明確に示した点にあります。これにより、研究者は慢性投与や用量反応関係を検討する必要性を認識し、次のステップへと進む基盤を得ました。さらに、研究は 安全性が確認された という重要な成果を残しています。今後の長期投与試験を進める上で不可欠なデータです。
・まとめ
CBDは若者のアルコール使用障害に対して「即効的な治療薬」とはならないことが今回の研究で示されました。しかし、これはCBDの可能性を否定するものではなく、慢性投与や適切な研究設計が必要であることを浮き彫りにした重要な知見です。今後、より長期的かつ精緻な研究が進めば、CBDが若者のAUD治療の一助となる日が来るかもしれません。
執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年9月2日
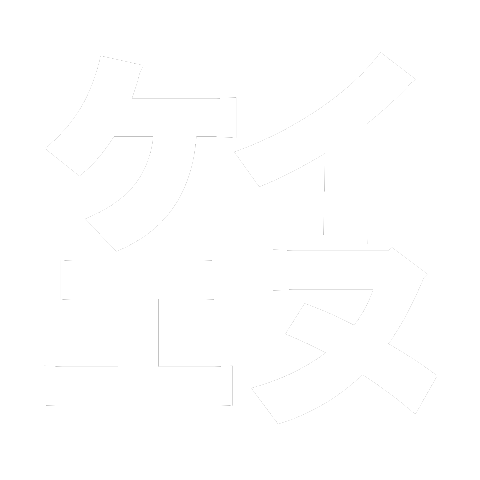

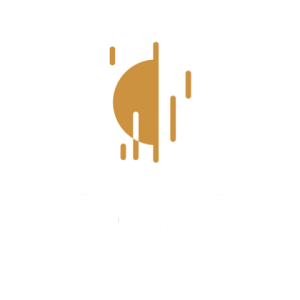
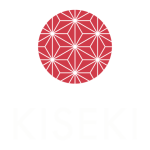
コメントを残す