・はじめに
近年、米国において医療用大麻(Medical Cannabis: MC)の合法化が急速に進んでいます。しかし、その臨床現場での利用については依然として明確な指針が不足しており、多くの医師が患者からの相談に十分に対応できない現状があります。本記事では、2025年に『Medical Cannabis and Cannabinoids』誌に掲載されたスコーピングレビュー論文「Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Perceptions about Medical Cannabis in the United States」をもとに、米国における医師の知識・態度・認識の現状を紹介します。
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12162117/
・医療用大麻の現状と法制度
米国では依然として連邦法上、大麻は「乱用の危険性が高く、医療的利用が認められていない」とされるスケジュールIに分類されています。しかし2023年、米国保健福祉省(HHS)は大麻をスケジュールIIIへ移行すべきと勧告しました。これは医療用途の可能性が認められたことを示しています。
現時点でFDAが承認している大麻由来薬は、てんかん発作に対するCBD製剤(Epidiolex)、化学療法に伴う悪心やエイズ関連カヘキシアに対する合成THC製剤(ドロナビノール、ナビロン)などわずかに限られています。
州レベルでは、47州とワシントンDC、さらに3つの海外領土で医療用大麻が合法化されており、そのうち38州では包括的なプログラムが導入されています。慢性疼痛が最も多い適応疾患であり、患者は「メディカルマリファナカード」を取得し、州認可のディスペンサリーで入手します。世論調査では約7割の米国民が合法化を支持しており、社会的後押しも強い状況です。
・本研究の方法
本レビューはPRISMA-ScRガイドラインに基づいて実施され、2013年1月から2025年2月までに発表された41本の研究が分析対象となりました。対象は米国内の医師、医学生、その他の医療従事者で、主に電子調査やインタビューにより、知識・態度・認識を評価しています。
・診療科ごとの理解度ランキング
本レビューをもとに、診療科ごとの「医療用大麻への前向きさ」をランキング形式で整理しました。
1位 小児腫瘍科
がん患児への使用を多くの医師が支持。患者や家族の要望に応える姿勢が強い。
2位 成人腫瘍科
高齢者には慎重だが、悪心・疼痛・食欲不振・抑うつなどに効果的と評価。
3位 緩和ケア科
疼痛・不眠・食欲不振・情緒的苦痛の軽減に有益。ただし実際に推奨した割合は半数未満。
4位 皮膚科
乾癬やアトピー性皮膚炎など炎症性皮膚疾患の外用利用に前向き。
5位 救急科
慢性疼痛や悪心には有効とみるが、急性副作用(不安発作、嘔吐症候群、交通事故)への対応経験から否定的態度も多い。
6位 家庭医(開業医)
全体的に懐疑的で、教育不足を強調。
7位 一般小児科(腫瘍科を除く)
CBD製剤の有効性を一部認めるが、神経発達への影響を懸念し慎重。
8位 精神科
不安障害などに効果を認めつつも、統合失調症リスクや妊婦への利用に強く否定的。
9位 産科
妊娠期での利用は否定的。児童保護への通報を説明するケースも。
10位 神経内科
てんかん治療に関して依然スティグマが強く、積極的ではない。
・医師の知識不足と教育の必要性
多くの医師がカンナビノイドの薬理、適応疾患、副作用、薬物相互作用などの基本的知識に不安を抱えており、患者指導や推奨の障壁となっています。→ CME(継続医学教育)や学会発表を通じた教育拡充、医学教育課程への体系的導入が求められています。
・地域性・文化的要因の影響
西海岸など合法化が進む地域 → 比較的前向き
南部や農村部 → 否定的態度が多い
地域社会の文化的背景や患者層の違いも影響しています。
・患者のニーズと現場のギャップ
患者の要望:慢性疼痛、不眠、悪心、食欲不振、オピオイド代替としてMCを求める声が増加。
医師の現状:知識不足により明確な指導ができず、患者が自己判断で利用を続けるケースが多い。
→ この「患者のニーズ」と「医師の準備不足」のギャップが臨床現場の混乱を生んでいます。
・倫理的・法的課題
州法では合法でも連邦法では依然として禁止薬物。医師は「処方」ではなく「推奨」という曖昧な立場。妊娠中や未成年者への使用は、医学的根拠に加えて倫理的観点からも難しい判断を迫られる。
今後の展望と日本への示唆
本レビューは米国を対象としていますが、日本にとっても重要な示唆があります。
医学教育にカンナビノイド薬理学を導入すること
専門医研修やCMEでの臨床応用教育の充実
倫理的・法的リスクを理解しつつ患者と建設的に対話するスキルの育成
米国での知見は、今後の日本での議論にも大いに参考となるでしょう。
執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年9月2日
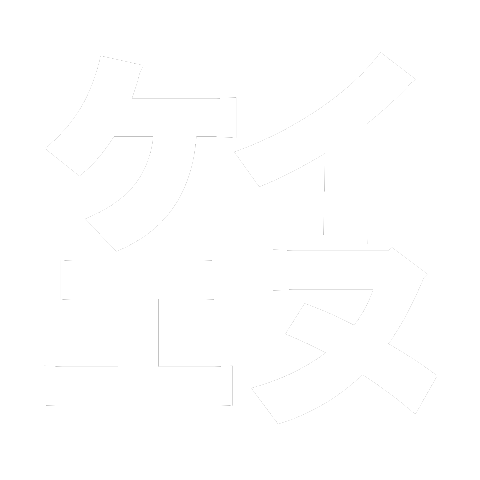

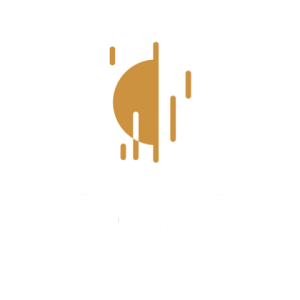
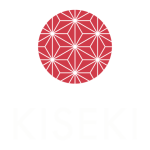
コメントを残す