片頭痛は世界で10億人以上が悩まされている一般的な疾患です。日本でも患者数は多く、日常生活や仕事に大きな支障をきたすことが知られています。従来の治療は大きく分けて、発作が起きてからの対症療法と、発作を未然に防ぐ予防療法の二つがあります。しかし、既存薬が効かない患者も少なくなく、新しい治療法が求められています。近年注目されているのが、大麻由来の成分(フィトカンナビノイド)や体内で作られる内因性カンナビノイド(エンドカンナビノイド)です。
我々は2020年に偏頭痛と医療大麻についての記事を公開しています。
本記事では、2020年以降の最新の研究成果を中心に、片頭痛とカンナビノイドの関係を解説します。
①三次医療機関の頭痛外来でわかったこと:片頭痛とカンナビス製品の「使い方」と「体感効果」(2024年・アメリカ)
本研究は、米国の三次医療機関(専門頭痛センター)の患者さんを対象とし「片頭痛に対して、大麻由来の製品を実際にどう使っていて、どんな体感効果があるのか」を大規模にアンケートした研究です。
・どんな研究ですか?
対象:米国コネチカット州の専門頭痛センターで受診歴のある患者
方法:過去3か月に受診した5,400人へオンライン調査(匿名・1回のみ)を案内し、1,373人が回答(回収率25.4%)
聞いた内容:
過去3年のカンナビス製品の使用有無・目的
製品の種類(吸入、食用、オイル、外用など)・THC/CBDの配合
片頭痛の頻度・強さ・持続時間への影響
随伴症状(吐き気、光過敏・音過敏、ブレインフォグ、食欲など)
睡眠・不安・抑うつなどの関連因子への影響
副作用、やめた理由、使わない理由 ほか
評価:各項目の「改善度」を6段階リッカート尺度で自己評価してもらいました。
・どれくらいの人が使っていましたか?
過去3年に使った:55.7%
現在も使っている:32.5%(全体の約3人に1人)
使う主な目的:片頭痛などの頭痛の症状対策(65.8%)、睡眠の改善(50.8%)
入手先:医療用ディスペンサリー(49%)、一般のストア(42%)など
製品のタイプ:食用(エディブル)75.4%、喫煙55.3%、ベイプ48.2%、オイル36.1%
成分の組み合わせ:THC/CBDのブレンドが最多(44.4%)でした。
・どんな「体感効果」が報告されましたか?
使用経験者の自己申告として、次のような改善が多く挙がりました。
・頭痛そのもの
強さ:78.1%が何らかの改善(そのうち「とても/極めて改善」47.8%)
持続時間:73.4%が改善(「とても/極めて」37.2%)
日数(頻度):62.4%が改善(「とても/極めて」24.5%)
服用薬の変化:48.9%が頭痛薬の量を減らせた、14.5%は他の薬を中止できたと回答
使い方の傾向:発作時だけ使うが58.0%、予防目的でほぼ毎日が42.0%でした。
・随伴症状・関連症状
吐き気:56.3%が改善(「とても/極めて」37.0%)
食欲:37.8%が「とても/極めて」改善
光・音過敏、ブレインフォグ:一部で改善報告はあるものの、改善度は比較的控えめでした。
・片頭痛に関係するリスク因子
睡眠:81.2%が改善(「とても/極めて」63.8%)
不安:47.1%が「とても/極めて」改善
抑うつ:31.4%が「とても/極めて」改善
全般的な痛み:45.3%が「とても/極めて」改善と回答しました。
・どんな人に効きやすい傾向が見えましたか?
月15日未満の頭痛の人は、月15日以上の慢性片頭痛の人よりも、頭痛日数の減少と睡眠改善の体感が強い傾向がありました。利用目的が多い人(3つ以上)ほど、頭痛・随伴症状・睡眠・気分など幅広い項目で「役立つ」と感じていました。(※あくまで自己申告の傾向であり、因果関係は証明できません。)
・副作用や「使わない理由」は?
副作用:20.9%が何らかの副作用を報告。多かったのはだるさ/倦怠感、ついで不安、食欲の変化、頭痛の悪化など。嘔気・嘔吐や被害感(パラノイア)などは少数でした。
使わない主な理由(非使用者のうち):何を選べばよいかわからない(54.1%)、用量がわからない(48.0%)、どこで買えばいいかわからない(約40%)、不安感・費用・職場や検査への配慮・医師から勧められていない・効くか不明などが挙がりました。
・この研究から言えること(示唆)
専門外来に通う片頭痛患者さんのかなりの割合が、頭痛や睡眠のために大麻製品を使っており、痛みの強さ・持続時間・吐き気・睡眠・不安などで自己申告の改善を感じている人が多いことがわかりました。THC/CBDブレンドを選ぶ人が多く、食用・吸入の使用が中心でした。
・この研究から言えないこと(限界)
自己申告のアンケートであり、プラセボ対照や医師評価ではありません。
偏頭痛に対してどの成分・どの用量・どの投与法が最もよいかは、この研究からは断定できません。
副作用や長期安全性、薬物相互作用の厳密な評価も未実施です。
調査実施地域(法制度や入手性)に依存する可能性があり、他地域にそのまま当てはめられない点に注意が必要です。著者らも、予防・急性期を含む厳密な臨床試験(RCT)が今後必要だと結論づけています。
・まとめ
専門頭痛外来の患者さん1,373人の調査で、半数超が過去3年に大麻製品を使用しており、頭痛の強さ・持続時間・吐き気、睡眠・不安などに関して体感的な改善を報告しました。一方で、科学的に「効く」と証明する研究(RCT)は不足しており、最適な成分・用量・投与法はまだ定まっていません。安全性や相互作用、長期使用のリスクを踏まえ、医療者と相談しながら活用の是非を検討することが大切です。
②大麻オイルの内服は「慢性片頭痛」に効くのか?——イタリア頭痛センターの後ろ向き研究
この研究では、イタリアの大学病院の頭痛センターで行われた経口カンナビノイド製剤(オイル)の実臨床データを解析しています。結論から言うと、「発作日数そのもの」はあまり変わらない一方、「痛みの強さ」や「頓用鎮痛薬の量・鎮痛薬を飲む日数」は減ったという結果でした。研究は小規模・非対照の後ろ向き調査であり、最終的な有効性を断言できる段階ではありませんが、日常診療のヒントになる所見が得られています。
・どんな研究ですか?
対象:慢性片頭痛(CM)の患者32名(女性84%・平均52歳)
期間:大麻オイル処方開始後3か月・6か月時点での変化を診療記録から評価
介入:医師が処方した大麻オイル(オリーブオイルにて希釈)3種類
FM2:THC 5–8%、CBD 7.5–12%
Bedrocan:THC 19–22%、CBD <1%
Bediol:THC 6.5%、CBD 8%(※本研究では1名のみ)
いずれも1日10〜25滴(最大1mL)の範囲で、各人一定用量を継続しました。
並行治療:他の予防薬を併用中でもOK(用量は固定)。評価項目は1.月間片頭痛日数(MMD)2.痛み強度(NRSスコア)3.月間の頓服薬の使用回数(AC)4.急性期薬を飲んだ日数(NDM)5.吐き気・嘔吐など随伴症状、有害事象でした。
参加者の多くは長年の難治例で、月28日前後が頭痛日、頓用薬の多用、併存症(精神科・リウマチ系など)も多いというかなり重症の患者像でした。
・結果:何がどのくらい良くなったのですか?
・発作日数(MMD)
有意な減少なし。ベースライン約28日/月 → 3か月・6か月でも統計学的有意差は出ず。
→「起きる回数」自体を下げる効果は明確でないという結果になります。
・痛みの強さ(NRS)
有意に低下。平均9.6 → 7.2 → 6.4と改善しました。
→「痛みの質・強さ」は和らいだと解釈できます。
・頓服薬の使用(量・日数)
使用回数(AC):83.8回/月 → 36.2 → 25.0 と大きく減少
服用日数(NDM):26.7日/月 → 20.4 → 17.4 と減少
→ 「レスキュー薬に頼る頻度」が下がった点は、生活のしやすさや薬物乱用頭痛の予防に関わる重要な所見です。
・吐き気・嘔吐
有意に減少(ベースライン94% → 6か月59%)。
→ 片頭痛のつらい随伴症状にも一定の緩和が見られました。
・製剤間の差・予防薬の併用差
FM2 vs Bedrocanで差は明確でない、予防薬の併用有無でも差は小さいという解析でした。
・安全性はどうでしたか?
有害事象:43.8%で何らかの副作用(多くは軽度の眠気)。中止は2名(6.3%)のめまいで、重篤な有害事象はありませんでした。
→ 眠気・ふらつきは運転・危険作業に注意が必要です。オイルでも初回は少量からが原則です。
・研究の限界
非対照・後ろ向き・少数例(n=32)、観察期間6か月
用量や製剤が人により異なる、Bediolは1例のみで比較困難
プラセボ効果を排除できない、長期安全性は未評価
→ したがって「効く」と断言する段階ではないことにご注意ください。今後は大規模ランダム化比較試験が必要です。
・まとめ
大麻オイルの内服は、慢性片頭痛の発作日数を明確に減らす証拠は示せませんでしたが、痛みの強さ、吐き気、頓用薬の量・日数の改善が観察されました。副作用は主に軽度で、中止は少数でした。ただし、この研究は小規模かつ非対照であり、結論は暫定的です。今後の厳密な臨床試験の結果を待ちながら、個別の目標設定と安全対策のもとで活用の是非を検討するのが現実的です。
③大麻の吸入摂取は発作中の片頭痛に効くのか?—初のランダム化比較試験
この研究は片頭痛の発作が起きた“その時”に、蒸気化した大麻を使うと効くのか?を検証した、初のランダム化二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験(RCT)です。結論からお伝えすると、THCとCBDを組み合わせたレジメンは、2時間後の痛みの改善や痛みゼロ達成率でプラセボより優れていました。いっぽう、CBD単独投与では明確な差が出ませんでした。
・どんな研究ですか?
対象:21〜65歳の片頭痛患者
デザイン:ランダム化・二重盲検・プラセボ対照・クロスオーバー
参加者は最大4回の片頭痛発作を、①THC優位(6%THC)②CBD優位(11%CBD)③THC+CBD(6%+11%)④プラセボのいずれかを1回ずつで治療(順番はランダム)
各発作の間は1週間以上あける(ウォッシュアウト)
投与方法:温度や吸引時間を統一した標準化パフ手順で蒸気化して吸入
評価時点:1・2・24・48時間後
主要評価項目(2時間):1.痛み軽減(moderate/severe→mild/none 2.痛みゼロ 3.最も煩わしい随伴症状(MBS=光過敏・音過敏・吐き気のうち本人が選択)の消失
・何人が参加して、どのくらいデータが集まりましたか?
登録92人、解析対象は247回の片頭痛発作(ITTでは未回答は不成功として扱う厳しめのルール)でした。
・主な結果:2時間後にどうなった?
1) 痛み軽減(主要評価)
THC+CBD群:67.2%が達成(プラセボ群46.6%より有意に高い)
THC優位群:68.9%で達成(プラセボ群より有意に高い)
CBD優位群:有意差なし(52.6%)
→ “痛みが弱まる”ことに関しては、THC+CBD群とTHC単独群が有利でした。
2) 痛みゼロ(痛み消失)の達成率
THC+CBD群:34.5%が達成(プラセボ群の15.5%より有意)
THC優位群/CBD優位群:いずれもプラセボ群と比較し有意差なし
→ “完全に痛みが消える”ことをアウトカムとした場合、THC+CBD群のみがプラセボを上回りました。
3) 最も煩わしい随伴症状(MBS)の消失
THC+CBD群:60.3%が達成(プラセボ群34.5%より有意)
THC優位群/CBD優位群:いずれもプラセボ群と比較し有意差なし
→光過敏・音過敏・吐き気のうち本人が選んだ最優先症状の消失も、THC+CBD群で優位でした。
・持続効果は?
THC+CBD群では24時間後の持続的な痛みゼロやMBS消失、さらに48時間後の持続的MBS消失でもプラセボ群より良好でした。一方で、THC単独群・CBD単独群はこれらの持続アウトカムでは優位性がみられませんでした。
・随伴症状への効果は?
2時間時点で、THC+CBD群は光過敏・音過敏の軽減でプラセボより優れていました(吐き気・嘔吐では差が出ず)。これは発作開始時点で光・音過敏の出現率が高かった一方、吐き気はやや低めだった影響も考えられます。
・安全性と陶酔作用の感じ方
重篤な有害事象はなし
主観的な陶酔作用はTHC単独>THC+CBD>CBD単独>プラセボの順で強く、THC+CBDはTHC単独よりも陶酔感・多幸感・認知への影響が少なめでした。著者らは、CBDがCB1受容体の“負のアロステリック調節”として働き、THCの精神作用を弱める可能性に言及しています。なお、本試験のTHC濃度(6%)は一般の市販品より低めで、高濃度である必要はないことを示唆する一材料とされています。
・研究の強みと限界
強み:
初のRCTとして急性期(発作時)の有効性を厳密に検証。
エピソード型と慢性型の両方を含み、実臨床への一般化可能性を意識した設計。
限界:
THC・CBD以外(マイナーカンナビノイドやテルペン)は検討せず、濃度や比率は単一設定。
単回投与のみで、長期的な反復使用の効果・リスク(薬物乱用頭痛や使用障害など)は未評価。
1〜2時間の即時効果を主要にみており、予防効果は対象外。
・実生活ではどう考えればよいですか?(一般的注意)
1.発作が来たときにTHC+CBDの吸入は2時間の痛み・MBSに有利という初のRCT結果です。
2.今回の条件ではCBD単独はプラセボと差が出ませんでした。
3.THCが入ると運転・危険作業は不可です。眠気・注意力低下に気をつけましょう。
4.低〜中等度濃度でもベネフィットが示唆されました。むしろ副作用を抑える設計が重要です。
5.国・地域で合法性や入手経路が異なります。他の薬との相互作用も含め、医療者に相談してください。
執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年8月20日
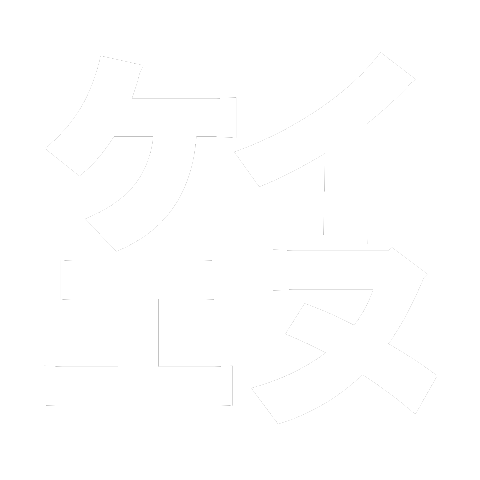

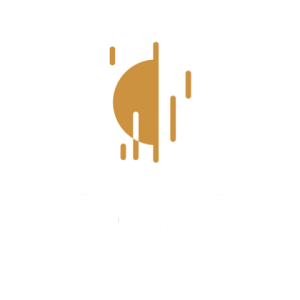
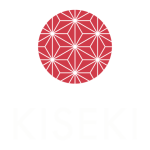
コメントを残す