はじめに:大麻をどう語るかは社会の鏡
大麻をめぐる議論は、いま世界中で加速しています。医療・健康・文化・経済。さまざまな側面が交差し、単なる「賛成か反対か」では語れない複雑なテーマになりつつあります。
スペインの研究チームが2025年に発表した論文、「Understanding the online landscape of cannabis discourse」(Frontiers in Public Health掲載)ではSNS上にあふれる“大麻の声”を科学的に分析するというユニークな試みが行われました。彼らは、2018〜2022年に投稿されたスペイン語のツイート約6万8千件を収集し、AIを使って内容と感情を分類しました。その結果、現代社会がどのように大麻を捉えているのか、とくに合法化や医療利用への考え方が浮かび上がりました。
方法:AIが読み解く「デジタル民意」
研究チームは、「cannabis」「marihuana」「hachís(ハシシュ)」という語を含むツイートを対象に収集。そのうち内容の明確な約3万4千件をAIによって精密に解析しました。
ツイートの分類は、人間の研究者がまず500件ずつ手作業で仕分けし、それをAI(BERTweet)に学習させて自動化するという方法です。分類の軸は次の通りです。
・大麻合法化への賛否
・医療・治療目的での利用に対する賛否
・健康リスクへの言及の有無
・投稿者の属性(一般人/メディア/政治家)
・投稿の感情(肯定的・否定的・中立)
AIによる分析は精度が高く、社会のリアルな声を統計的に捉えることができました。
まさに、SNSを「新しい世論調査」として使う発想です。
結果1:7割以上が合法化を支持 ― 「もう止められない潮流」
結果は明確でした。全体の73.2%が大麻の合法化に賛成、反対はわずか3.5%に留まり、残りは中立でした。これは、少なくともスペイン語圏のSNSにおいて、「大麻を全面的に禁止する時代は終わりつつある」という社会の空気を示しています。賛成派の多くは、「大麻は他のドラッグより安全」、「犯罪抑止や税収の増加につながる」、「個人の自由として認めるべき」といった理由を挙げていました。この結果は、アメリカやカナダなどで実際に進んだ合法化の流れとも一致しています。研究者らは、SNS上の言論が政策形成に影響を与える可能性を指摘しています。
結果2:医療大麻への期待 ― 科学と人々の意識が近づく
一方で、医療大麻の利用を支持する投稿は30%前後にとどまりました。ただし、これは「医療利用に否定的」というより、「治療の詳細を知らない層が多い」ことの裏返しだと考えられます。実際、医療大麻には多くの科学的エビデンスが蓄積しつつあります。てんかん、慢性疼痛、多発性硬化症、がん関連の食欲不振など、いくつかの病態ではCBD(カンナビジオール)やTHCを利用した薬剤がすでに承認されています。SNS上での議論が医療情報の共有を促す可能性もあり、研究チームは「医療従事者が積極的にSNSに参加することが重要」と提言しています。
結果3:ポジティブな感情が優勢 ― 大麻は“癒し”と“希望”の象徴?
投稿全体のうち17.3%がポジティブな感情を含み、残りは中立またはネガティブでした。ただし、投稿の拡散数(リツイート・いいね数)を見ると、最も影響力が大きいのは大麻の肯定的な側面を語るツイートでした。「痛みが和らいだ」「不安が軽くなった」「人生が変わった」そうした体験談が多くの共感を呼び、社会の認識を変えつつあるのです。興味深いのは、実際の使用者の投稿が全体のわずか2.5%しかないにもかかわらず、彼らの発信が最も多く拡散されたという点です。つまり、少数のリアルな声が世論の中心を動かしているとも言えます。
結果4:スペインと中南米が発信の中心
地理的には、ツイートの約8割がスペイン、チリ、アルゼンチン、メキシコ、コロンビアから発信されていました。これらの国々では、すでに医療大麻が一定範囲で認められており、市民の間でも「合法化は現実的な政策課題」として語られています。特に南米諸国では、経済的観点からも大麻産業への関心が高く、「国産医療用カンナビスの栽培・輸出を支援すべき」という声も増えています。大麻を“問題”としてではなく、“機会”としてとらえる視点が広がりつつあるのです。
結論:大麻を語ることは、社会を語ること
この研究は、単にツイートを数えた分析ではありません。そこには、「社会はどう変わるのか」「私たちは何を信じているのか」という、より深い問いが隠れています。
・SNS上では、すでに大麻合法化が主流の意見になりつつある
・健康リスクを冷静に議論する空気が求められている
・医療大麻と娯楽大麻の境界を理解する教育が必要
そして何より、人々の声を可視化するツールとしてSNSを活用する意義を示しました。大麻をめぐる議論は、もはや“道徳”ではなく“科学と政策”の問題。その未来をつくるのは、冷静に情報を発信し、共有する私たち一人ひとりです。
参考文献:
Alvarez-Mon MA et al. (2025). Understanding the online landscape of cannabis discourse: a Twitter analysis. Frontiers in Public Health, 13: 1416171. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1416171
執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年10月13日
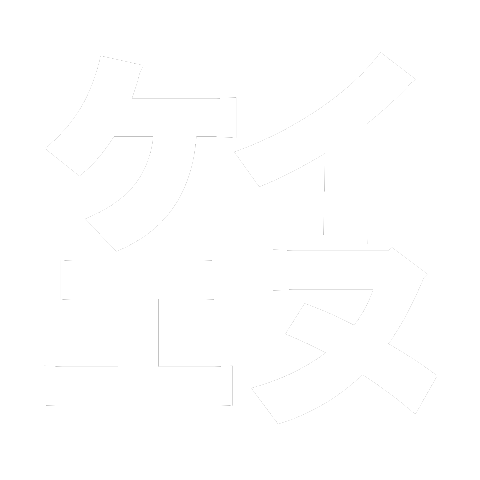

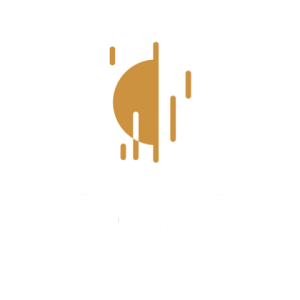
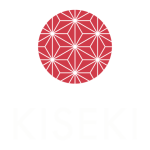
コメントを残す